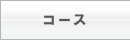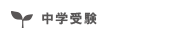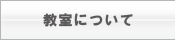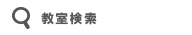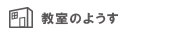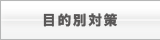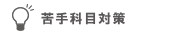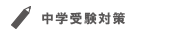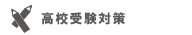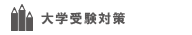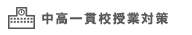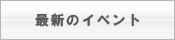���m�点
�V�w�N�˓�!!
����ɂ��́B�u�t�̓c���ł��B
�S���ɓ���A���悢��V�w�N�ɓ˓����܂����ˁB
�V���������A�V�������ȏ��A�V�����m�[�g�E�E�E
�C�������S�@��]�I
�u���܂łň�Ԃ̎����v�ɕϐg���Ċ撣���Ă����܂��傤�I�I
���ȏ��ƈꏏ�ɂ��炤���[�N��h�����̐i�ߕ���
������x�m�F���Ă����܂��傤�B
�������������Ă��錾�t
�u���[�N�͍Œ�Q��A�ō��o����܂ł�肱�ގ��I�I�v
�����S�����Ă��鐶�k�͂������Ƀ^�R���Ǝv���܂�(��)
�@���[�N�͕K���m�[�g�ɂ��
�A�P�y�[�W�������ەt��������
�B�~�X�������ɖڈ������
�C�~�X�������̉�����悭�ǂ�ʼn����Ȃ���
�@�ǂ�ł�������Ȃ����͐搶�Ɏ��₷��
�D�@�`�C���J��Ԃ�
�E�e�X�g�O�͖ڈ�̕t�����Ƃ����������x������
���̎菇����������Ǝ����
���[�N�}�X�^�[�ɂȂ�A�������Ƃ���G�Ȃ��ł���I
�������点�邮�炢����ɗ��Ă��������B
���҂����Ă܂���
�������̂��b
����ɂ��́B�u�t�̓c���ł��B
�����Ȃ�Ƒ��������Ȃ�܂���ˁB�~�̏펯�ł��ˁB
�ł��A�Ƃ��Ă������̂ɂ��̏펯���������Ȃ��ꏊ�������ł��B
�Y�o���I�u�k�ɁE��Ɂv�ł��B
�k�ɂ��ɂ͂��̂����������̂ɑ��������Ȃ�Ȃ��I
�Ȃ��ł��傤�H�I
���������Ȃ�ɂ͂Q�̏�����������Ă��Ȃ��Ƃ����܂���B
�P�ڂ͊O�̋C�����̓��̋C����肸���ƒႢ���ƁB
2�ڂ͐����C���t�����邽�߂́u�j�i�`����ق����ڂɌ����Ȃ��S�~�Ȃǁj�v�����邱�ƁB
�ł�
��������������̂́u�j�v�Ɂu�����C�v���������Đ��H�ɂȂ邩��ł��B
��C�����ꂢ������ꏊ�ł͂Q�ڂ̏����ł���u�j�v�����݂��܂���B
�Ȃ̂ŁA������o�������C�����H�ɂȂ�Ȃ��̂Ŕ��������Ȃ�
�Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�s�v�c�ł��ˁ`�I�ʔ����ł��ˁ`�I
����ȂƂ��납�痝�Ȃɋ����������Ă����̂������ł��ˁI
�O��̃N�C�Y�̓����E�E�E
�ÓT���͂ɏo�Ă��鏕�����u�`����v��t���ďI�����̂��������Ƃ���A�������}���邱�Ƃ��o�����Ƃ����Ӗ��Ŏg���邱�Ƃ������Ȃ��������ł��B
���������悤�ȁE�Z�������悤�Ȏ����Ƀs���I�h��łĂ��Ǝv������A
���ꂩ��͐V�����w�Z�ŁA�V���Ȑ����̃X�^�[�g�ł��ˁB
�P����t���Ă��A�����Ă������A�܂��V���������҂��Ă��܂��B
�y���݂Ȃ���A����H������Ȃ���A���ɂ͎̋�J���v���o���Ȃ���A���z���@�撣���ė~�����ȁE�E�E
�ƐV�����w�Z�������[������悤�F���Ă��܂��B
�s�������܂� ����12��
�����Ɍ��_���o���ďI���ɂ��邱�Ƃ��u���������v�Ƃ����܂����A���́u����v�Ƃ͉��̂��Ƃł��傤�H
�s�����w�܂Ł@���ƂP�Q��
����������Â������C�����Ɂu�P����t���āv�A���ƂP�Q���@�������I�̓����������܂��傤�I
�����́A����`��
- �ʎw���m�m�[�o�X >
- �����s >
- ���q�Z >
- ���m�点


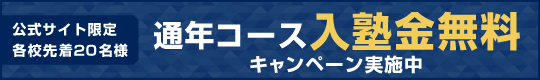










 ���m�点�S��
���m�点�S��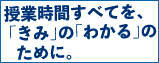



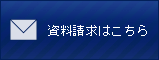
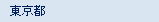
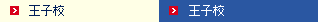
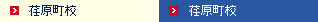
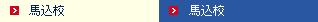
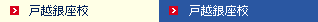
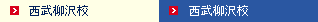
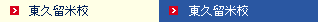
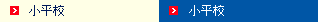
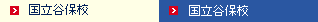
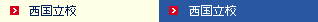
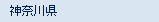
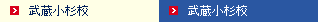
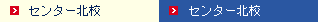
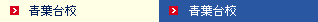
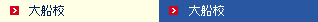
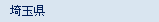
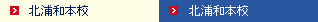
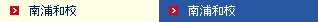
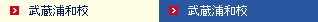
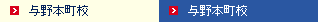
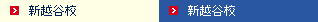
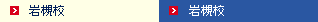
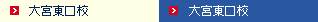
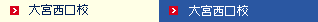
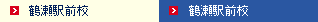
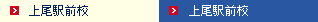
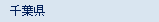
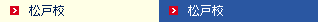
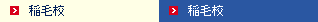
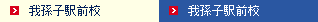
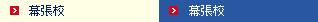
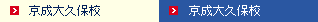
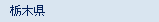
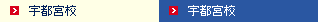
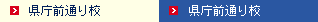
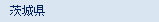
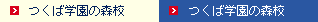
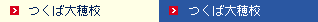
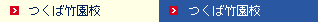
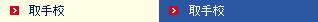
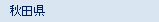
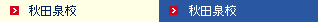
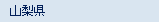
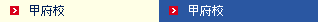
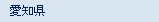
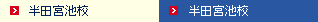
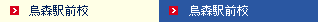
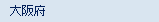
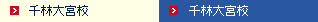
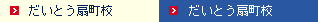
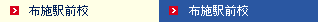
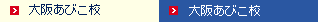
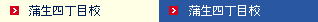
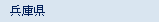
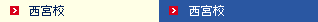
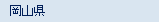
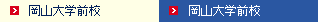
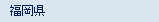
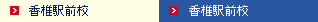
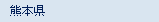
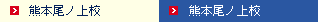

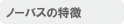

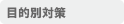




 2025-11-04
2025-11-04 2025-03-06
2025-03-06 2025-02-28
2025-02-28 2024-09-02
2024-09-02 2024-03-08
2024-03-08 2023-09-11
2023-09-11 2023-09-05
2023-09-05 2023-08-07
2023-08-07 2022-12-08
2022-12-08 2022-09-27
2022-09-27 2022-09-01
2022-09-01 2022-06-17
2022-06-17 2022-06-17
2022-06-17 2022-05-16
2022-05-16 2022-05-09
2022-05-09 2022-02-25
2022-02-25 2021-11-19
2021-11-19 2021-09-01
2021-09-01 2021-05-06
2021-05-06 2025-11-08 �����Y�a�Z
2025-11-08 �����Y�a�Z 2025-11-08 ��эZ
2025-11-08 ��эZ 2025-11-08 ���q�Z
2025-11-08 ���q�Z 2025-11-08 ��{�����Z
2025-11-08 ��{�����Z 2025-11-07 �ߐ��w�O�Z
2025-11-07 �ߐ��w�O�Z 2025-11-07 ��D�Z
2025-11-07 ��D�Z 2025-11-07 ���ˍZ
2025-11-07 ���ˍZ 2025-11-07 �`�����Z
2025-11-07 �`�����Z 2025-11-06 �����Z
2025-11-06 �����Z 2025-11-06 �k�Y�a�{�Z
2025-11-06 �k�Y�a�{�Z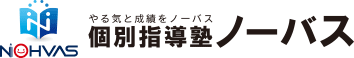


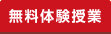

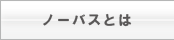

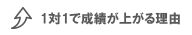

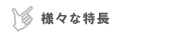
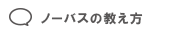
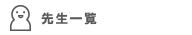

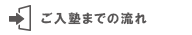

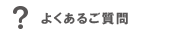
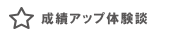
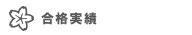
![���i�̌��L�i���R�~�E�]���j](https://www.nohvas-juku.com/library/images/menu/mainmenu_nakami_1-13.gif)