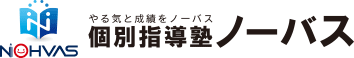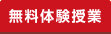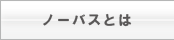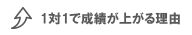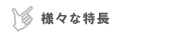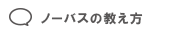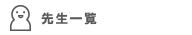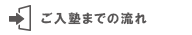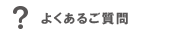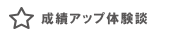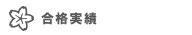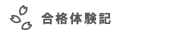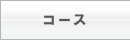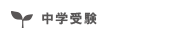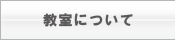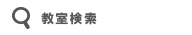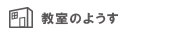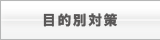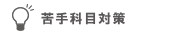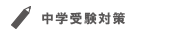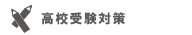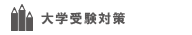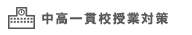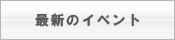お知らせ
公民を攻略しよう!
 こんにちは。ノーバス荏原町校です。
こんにちは。ノーバス荏原町校です。本日は、特に高校受験生向けに公民について述べていきます。
地理や歴史と比べて、公民は聞き慣れない言葉が次々と登場し、制度の仕組みも複雑に見える。
苦手意識を持ってしまうのも無理はありません。
しかし、実は公民は「正しい学習法」を知っているかどうかで、得点の伸びが大きく変わる科目なのです。
ポイントを押さえて学習すれば、安定して高得点を取ることが可能になります。
そこで、公民の特徴を踏まえた効果的な学習法と、入試本番で得点力を発揮するためのコツをお伝えします。
公民の特徴を理解しよう
公民が地理や歴史と大きく異なる点は、「初めて出会う用語が多いこと」と「制度や仕組みが複雑で理解しにくいこと」の2つです。
逆に言えば、攻略の鍵は明確です。
「用語をしっかり覚えること」と「仕組みを正しく理解すること」。
この2点に集中して学習を進めていきましょう。
基礎固めの進め方
用語の習得と仕組みの理解がある程度進むと、関連する問題の半分以上は解けるようになってきます。
間違えた問題に出てきた「知らなかった用語」や「理解が曖昧だった仕組み」は、その都度確認すれば十分です。
大切なのは、短時間の演習を繰り返すこと。正答できる問題を着実に増やし、知識を定着させていきましょう。
公民の4つの分野
公民は学習内容によって以下の4分野に整理できます。
現代社会:今の社会の姿や、社会のルールを学ぶ
政治の仕組み:社会の問題をどう解決するかを学ぶ
経済の仕組み:お金の働きや流れを学ぶ
国際社会:他国との関わり方を学ぶ
用語や仕組みが難しいと感じたときは、「これは日常生活のどの場面に関係しているのか」を想像してみてください。
選挙権のように、まだ実感が湧かないものもあるでしょう。
しかし、テレビで見たこと・ニュースで聞いたこと等と結びつけられれば、理解は一気に深まります。
テーマ学習の段階から応用問題に挑戦しよう
一問一答形式の問題で7〜8割正解できるようになったら、次のステップに進みましょう。
資料を読み取って「内容を説明する問題」「正誤を判断する問題」「理由を述べる問題」に取り組んでみてください。
最初は教科書やテキストで見たことのある資料が使われることが多いため、比較的解きやすく感じるはずです。
しかし、入試レベルの「初見の資料をもとに、その場で考えて答える」問題になると、難しさを感じることがあるかもしれません。
知識はあっても、問題の指示に沿って答えをまとめる力、つまり思考力・記述力が十分に鍛えられていないと、制限時間内に解答をまとめきれないのです。
こうした読解力や記述力は、入試直前の対策だけで身につくものではありません。
また、忘れてはならないのが、公民は中学3年間の最後に学ぶ科目だということ。
地理や歴史に比べて復習に充てられる時間が限られており、応用問題対策まで考えるとなおさらです。
だからこそ、公民の学習では「各テーマを学ぶたびに応用問題にも取り組むこと」を強くおすすめします。
学習直後に正解できなくても問題ありません。
重要なのは、「入試では何が問われるのか」「解くためにどんな力が必要なのか」を早い段階で知っておくことです。
学習を進める中で、資料の読み取り方・問題文の意図の正確な把握・解答のまとめ方が身についてくると、得点力は大きく向上していきます。
公民に限らず、受験勉強で「できない」と感じることがあっても、正しい方法でコツコツと努力を重ねれば、必ずできるようになります。
今回ご紹介した学習法を参考にして、受験を有利に進めていただけたら幸いです。
古文読解、最初のポイント!
 こんにちは。ノーバス荏原町校です。
こんにちは。ノーバス荏原町校です。生徒の皆さん、古文の学習はどうしていますか?
単語や文法の暗記を一生懸命頑張っている方も多いかと思います。
しかし!古文も現代文と同じ「文章」だということを忘れないでください。
単語や文法の知識だけでは、複数の意味を持つ言葉を正しく解釈できません。
まずは「文章として読む力」を身につけることが大切です。
そこで、今回は『伊勢物語』を例に出して解説していきます。
読む前の準備が大切
ドラマを観る時に、番組予告や友達からの情報で「これはアクションだな」「恋愛モノかな」等、予測しますよね。
古文も同じです。入試問題なら、注や選択肢からヒントが得られます!
例えば、『伊勢物語』のテーマは「恋愛」です。
基本情報として
・歌物語の代表作 → 和歌は恋の歌が多い
・在原業平がモデル → イケメン貴族が主人公
・『源氏物語』につながる → 源氏も恋愛物語
これらの情報から、『伊勢物語』が恋愛物語だと分かります。
そして、恋愛がテーマだとわかれば、展開も予測できます!
告白までの紆余曲折、邪魔が入る、裏切られる…といったパターンです。
恋愛物語の基本は男女1組のカップル。
まずはこのメインペアを見つけましょう。
周りの人物は、ライバル、協力者、障害となる人物です。
実際に読むときのコツ
本文を読むときは、分かることを確実につかむことが基本です。
恋愛物語なら、まずカップルを見つけ、次に出来事を追います。
まだ付き合っていないなら告白のタイミングと結果、すでに付き合っているなら別れの危機や障害は何か。
そして最終的にどうなるのかを確認します。
知らない単語や文法があっても、とりあえず先に進んでみましょう。
現代語の部分や、確実に理解できる部分を軸にして読み進めるのです。
不思議なことに、話の大筋と登場人物のイメージがつかめてくると、最初は「分からない」と思っていた部分も、なんとなく意味が推測できるようになってきます。
この読解力は、単語力や文法力とは別のものであり、それらと同じく訓練で確実に伸ばせる力なのです。
いかがでしたか。
古文読解の第一歩は、「古文も文章である」という当たり前のことを意識すること。
ジャンルとテーマを把握し、「分かる」を確実につかみながら、楽しみながら読み進めましょう!
暗記の時間帯を意識しよう!
 こんにちは。ノーバス荏原町校です。
こんにちは。ノーバス荏原町校です。「時間をかけているのに、なかなか暗記事項を覚えられなくて困っている…。」という方、多いのではないでしょうか。
実は、何を勉強するかだけでなく、いつ勉強するかも超重要なんです。
今回は、脳科学に基づいた効率的な暗記のための時間帯と、実践的なコツを紹介します!
時間帯で暗記効率が変わるって本当?
結論から言うと、本当です。
人間の脳は時間帯によって働きが変わります。
記憶には「短期記憶」と「長期記憶」があり、勉強した直後は短期記憶として保存されますが、そのままだと時間が経つと忘れてしまいます。
重要なのは、いかに長期記憶に定着させるか。
そのカギを握るのが「睡眠」と「繰り返し」です。
部活などで忙しい皆さんには、効率的に暗記できる時間帯を狙った勉強法がおすすめです。
暗記のゴールデンタイム3選
1. 起床後(起床〜2時間)
朝は最強の暗記タイムです。
睡眠で疲れが取れた起床直後の脳は、1日で最もコンディションが良い状態。
記憶できる容量も最大で、「脳のゴールデンタイム」とも呼ばれています。
さらに、睡眠中に前日の記憶が整理されているため、前日の夜に覚えた内容を朝に復習すると、記憶がより深く定着します。
登校前の限られた時間という「締切効果」で集中力もアップ!
朝は暗記だけでなく、数学の難問や英語長文など、脳に負荷がかかる勉強にも最適な時間帯です。
2. 夕食後
リラックスしながら作業的に暗記するなら夕食後。
学校の疲れも取れてリラックスできる時間帯なので、英単語や地理の暗記など、単純な反復学習に向いています。
脳は日中の活動で疲れているので、難しい問題を解くより、考えずに進められる暗記がベスト。
音読しながら暗記すれば眠気対策にもなります。
ただし、食べ過ぎは禁物!
満腹だと眠くなってしまうので、腹八分目を意識しましょう!
3. 就寝前
就寝前は暗記の真のゴールデンタイムです。
記憶は睡眠中に定着しますが、特に就寝直前にインプットした情報は長期記憶として残りやすいことが分かっています。
時間帯別の勉強法を取り入れるなら、就寝前の暗記は絶対に外せません。
ただし、睡眠時間を削るのは逆効果!
終了時間を決めて、しっかり睡眠時間を確保することが大切です。
暗記効率をさらに上げる3つのコツ
1. 睡眠時間は絶対に確保する
記憶の定着には睡眠が不可欠です。
慢性的な睡眠不足は、徹夜と同レベルまで脳のパフォーマンスを下げてしまいます。
就寝前の勉強が効果的だからといって、夜更かしは絶対NG。
半身浴などで睡眠の質を高める工夫もおすすめです。
2. 適度な運動で気分転換
暗記は単調になりがちで、飽きやすいですよね。
適度な運動を取り入れると、眠気覚ましになるだけでなく、リラックス効果で脳の状態を良好に保てます。
特に朝のウォーキングは、「幸福ホルモン」セロトニンの分泌を促し、脳を覚醒させる効果があります。
3. スキマ時間を活用する
暗記は繰り返しの回数が勝負。
通学時間などのスキマ時間を活用して、暗記の回数を増やしましょう。
お風呂に防水の単語帳を持ち込むのもおすすめです!
暗記効率を上げるには、脳の働きに合わせた時間帯選びが重要です。
特に就寝前は最も効率的な暗記タイムで、起床後に前日の復習をすれば相乗効果が期待できます。
暗記が苦手な人こそ、時間帯を意識した勉強法を試してみてください。
地道に頑張っていけば、必ず結果はついてきます。
効率的な勉強法で、是非とも目標を達成していただきたいと思います!
メンタルケアをしてみよう!
 こんにちは。ノーバス荏原町校です。
こんにちは。ノーバス荏原町校です。本日は受験生に向けて、メンタルケアの話をしていきます。
「もう勉強したくない」「成績が上がらない」「現状のままで大丈夫か」
これらのような悩みを持つ生徒さんが多いのではないでしょうか。
特に今の時期は、精神的な負担が急増します。
しかし、心が疲れているのは、あなたが頑張ってきた証です。
適切に対処すれば、前向きな思考で学習を進めることができます!
デジタルデトックス
勉強中は通知をすべてオフにし、週1日はインターネットから離れてみましょう。
SNS等を見ないことで、他の受験生との比較による焦りから解放されます。
自然との接触
散歩を週3〜4回することで、副交感神経が優位になり、心が癒されます。
この時、空の色や風の香りを意識的に感じると更によいでしょう。
良質な睡眠
睡眠は決してムダではなく、学習効率とメンタルを支える最も大切な「土台」です。
毎日同じ時刻に寝起きし、就寝1時間前にスマートフォンを見ることは避けましょう。
感情の言語化
不安を抱え込まず、信頼できる人に話すか、日記に書き出してみましょう。
感情を表現することができ、心が軽くなります。
入試では、学力だけでなく「精神」と「身体」の総合力も試されます。
自分を信じ、自分を労わり、賢くメンタルケアをしてみてください。
あなたは一人ではありません。
ノーバス荏原町校の講師一同、全力で応援しています!


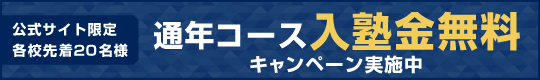









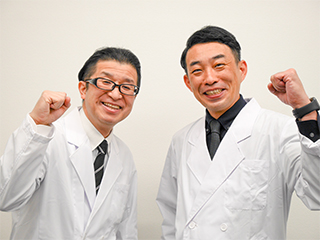
 お知らせ全て
お知らせ全て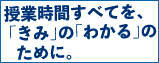



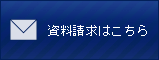
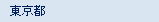
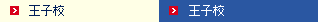
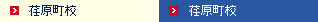
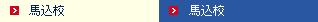
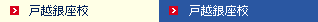
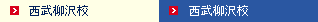
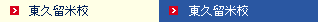
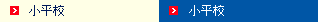
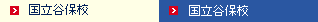
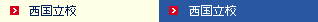
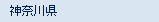
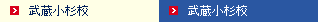
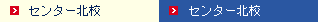
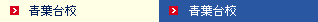
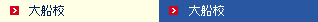
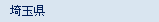
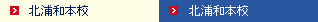
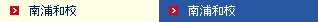
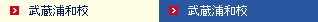
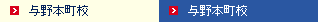
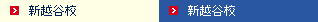
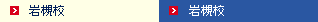
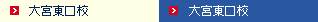
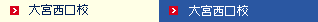
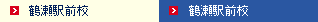
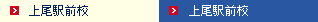
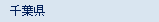
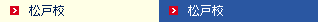
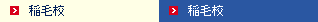
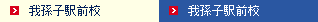
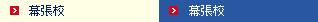
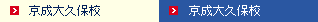
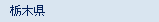
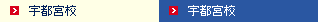
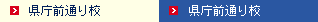
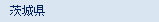
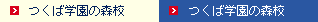
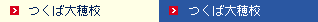
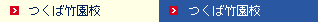
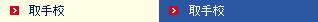
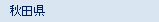
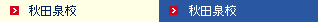
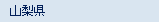
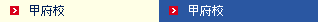
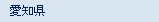
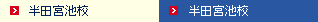
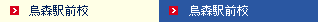
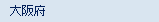
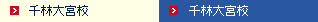
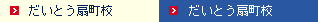
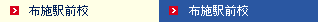
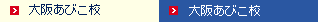
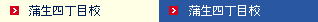
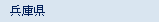
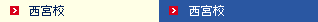
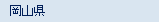
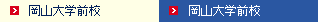
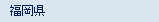
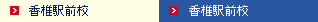
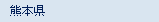
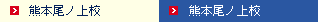

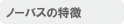

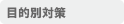




 2025-11-04
2025-11-04 2025-03-06
2025-03-06 2025-02-28
2025-02-28 2024-09-02
2024-09-02 2024-03-08
2024-03-08 2023-09-11
2023-09-11 2023-09-05
2023-09-05 2023-08-07
2023-08-07 2022-12-08
2022-12-08 2022-09-27
2022-09-27 2022-09-01
2022-09-01 2022-06-17
2022-06-17 2022-06-17
2022-06-17 2022-05-16
2022-05-16 2022-05-09
2022-05-09 2022-02-25
2022-02-25 2021-11-19
2021-11-19 2021-09-01
2021-09-01 2021-05-06
2021-05-06 2025-11-23 西宮校
2025-11-23 西宮校 2025-11-22 武蔵浦和校
2025-11-22 武蔵浦和校 2025-11-22 熊本尾ノ上校
2025-11-22 熊本尾ノ上校 2025-11-22 稲毛校
2025-11-22 稲毛校 2025-11-22 大船校
2025-11-22 大船校 2025-11-22 大宮東口校
2025-11-22 大宮東口校 2025-11-22 大宮西口校
2025-11-22 大宮西口校 2025-11-22 烏森駅前校
2025-11-22 烏森駅前校 2025-11-21 千林大宮校
2025-11-21 千林大宮校 2025-11-21 荏原町校
2025-11-21 荏原町校